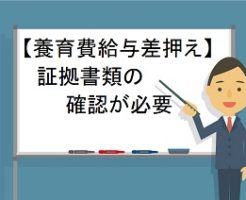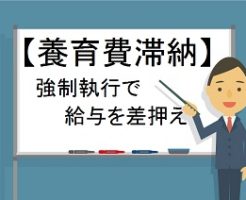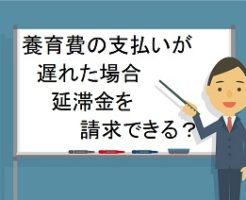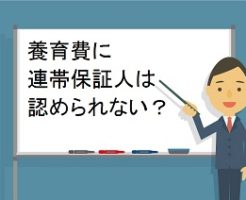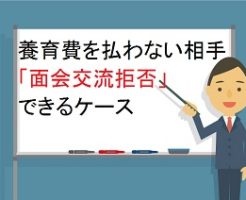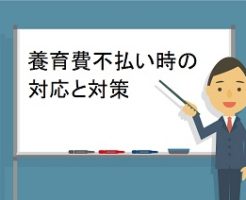養育費とは
そもそも養育費は「支払金額・回数・期間」などを明確に法律で規定されたものではありません。
養育費とは、親権者または監護者が子どもの代わりに扶養請求をおこない、その支払われたお金は、子どもの扶養のために使われるものなのです。
簡単に言うと、この子どもを育てるのに必要な費用とは、子どもが成人するまで、または大学を卒業し自立するまでの期間にかかる費用(衣食住の費用、教育費・娯楽費・医療費など)のことになります。
高校・大学進学時にかかる入学金などの一時的にかかる費用についても取り決めを行なっておくと良いでしょう。
この養育費について問題になるケースとして、「支払ってもらえない」「請求さえしていない」といったことがあげられます。
これらは離婚時に養育費の取り決めをしっかりと行なっていないことが原因です。
しかし養育費は払わなくていいというものではありませんので、支払いが止まったらちゃんと請求を行い、強制執行まで視野にいれて行動すべきなのです。
理想としては、離婚協議中にしっかりと取り決めを行い、不払いにならないような事前対策を行うことです。
そして離婚協議をうまく進めることができなければ、離婚問題に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
養育費は長期間に渡り支払われるため、途中で不払いが起こるケースも少なくありません。そのため、こういったリスクを未然に防ぐ取り決めをしておくことが重要です。
法律のプロフェッショナルである弁護士に依頼することで、将来の不払いのリスクを減らしておいては如何でしょうか?
地方自治体の補助金対象へ|養育費保証の養育費安心サポート
養育費の支払いが止まっても安心
・最低でも12回分の養育費を保証
・不払いとなっている養育費を立て替えるサービス
・無料で様々なサービスが付帯
・申込みからサービス開始まで安心のサポート!
あくまでも子どもの扶養のための費用
勘違いしてはならないのが、親権者は代わりに請求しているだけであり、あくまでも養育費は子どもの扶養のための費用なのです。
そのため家庭裁判所で養育費の調停を申し立てた場合、養育費の支払い先を養育費の受取人である子どもの口座に振り込むようにすることもあります。
また親権がない理由で、養育費の支払いの拒否、理由のない減額などはできません。
一般的な養育費の金額は、月に3~5万円程度ですが、この金額は支払者の経済状況より変動します。また養育者の収入が多い場合は、養育者の収入を考慮することもあります。
話し合いで合意できなった場合
支払い金額について、話し合いで合意できなった場合は、家裁の調停または審判で合意を目指すことになります。
上記同様に夫婦双方の収入や、子どもの人数、年齢などを考慮して、養育費の金額設定がされます。
ちなみにここで決定した金額は、正当な理由があれば、容易ではありませんが後々変更を求めることも可能です。これは双方の将来の経済状況を正確に予測することが不可能なための措置と言えます。
調停が成立すると、合意の内容で調停調書が作成されます。支払いが滞った場合には強制的に取り立てる手続きをとることができます。
また調停が不成立になった場合は、再度話し合いにもどるか、審判に移行します。審判に移行した場合は、家事審判官が審判を下す流れになるのです。
審判まで移行するケースでは、一度弁護士に相談することをおすすめします。
また養育費の調停は通常の家裁の調停とは異なり「子どもの住所地の家裁が管轄裁判所」となりますのでご注意ください。通常の家裁の調停は相手方の住所地の家庭裁判所に申し立てをします。
地方自治体の補助金対象へ|養育費保証の養育費安心サポート
養育費の支払いが止まっても安心
・最低でも12回分の養育費を保証
・不払いとなっている養育費を立て替えるサービス
・無料で様々なサービスが付帯
・申込みからサービス開始まで安心のサポート!
厚生労働省の調べ
厚生労働省の調べによると、決まった額の養育費の支払いを受けている、又は受けたことがある世帯の、養育費の平均月額は43,482円(平成23年度全国母子世帯等調査)となっています。
また家庭裁判所の公式サイトに掲載されている、養育費の算定表により、夫婦双方の収入や子どもの年齢などから、受け取り可能額を予想することができます。
しかし実際に養育費を受けているのは、母子家庭は19.7%、父子家庭は約4.1%(平成23年度全国母子世帯等調査)と、大半の世帯が養育費を受けていない現状が明らかになっています。
つまり支払われるべき養育費とそのた実態には大きな開きがあると言えるのです。
養育費の受給率が低い原因に、離婚時に養育費の取り決めをしっかり置かなっていないことが背景にあります。母子家庭では37.7%、父子家庭に至っては17.5%しか取り決めをしていないのです。
母子家庭の貧困の原因に
一般的に子どもを成人まで育てるために必要だと言われる3000万円程度を、子育てをしながらひとりでまかなうことは大変なことです。
養育費の支払い率の低さは、母子家庭の貧困という社会問題の一要因になっていると言えます。
また大学等(通信除く)の進学率を見ても、全世帯の進学率が53.7%に対して、母子・父子世帯では:23.9%とかなりの開きがあるのがおわかり頂けると思います。
1ヶ月当たり教育費に関しても、全世帯の平均:31,565円に対して、母子・父子世帯では16,291円と全世帯の52%程度になっているのです。
ここで活用すべきなのが公共団体の学習支援ボランティア事業である「ひとり親家庭の子供の学習支援」です。
塾や家庭教師を利用するのに近い形態で学習指導を受けることができます。さらに費用は原則無料ですので、活用しない手はないでしょう。
公正証書の重要さ
離婚時にしっかりと養育費の取り決めを行なうことで、養育費を確保できる確率はかなり上がります。
子どもの権利を守る為にも、離婚時には養育費について話し合い、内容を離婚協議書にし、出来る限り「公正証書」(離婚給付契約公正証書)を作成しておくことおすすめします。
公正証書を作成するには、下記が必要となります。
- 公正証書にした内容(離婚協議書など)
- 夫婦双方の運転免許証orパスポート(+住民票)or住民基本台帳カード(顔写真付き)と認印、または印鑑証明書と実印
- 戸籍謄本(全部事項証明。離婚後であれば双方の新しい戸籍)
原則として夫婦が揃って公証役場に出向き作成しますが、手続きを代理人に委託することもできます。
代理人依頼する場合は、委任状が必要になりますが、委任内容を事細かに記載する必要があるため、まずは公証役場にお問い合わせすることをお勧めします。
参考:「平成23年度全国母子世帯等調査」「平成26年度学校基本調査」を参考。
地方自治体の補助金対象へ|養育費保証の養育費安心サポート
養育費の支払いが止まっても安心
・最低でも12回分の養育費を保証
・不払いとなっている養育費を立て替えるサービス
・無料で様々なサービスが付帯
・申込みからサービス開始まで安心のサポート!