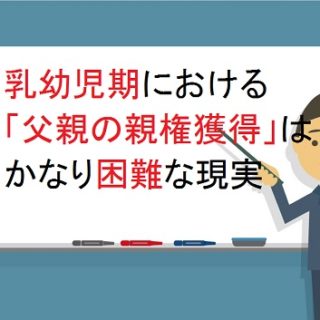やっぱり「母親」が有利!?
「子供を大切にできるのは、誰か」ということが親権を決定する基準です。
子供を大切にしたいと思う気持ちは親であれば「母親」も「父親」も同じでしょうが、思いだけでは実際に子供を大切にできないことがあるのはみなさんもご存知かもしれません。
「母親」と「父親」が「話し合って」も「親権者」が決まらない場合、「裁判所」がどちらの親を「親権者」としたほうが子供の幸せかということを考慮して決めることになっています。
離婚することは話し合いで決定していて、どちらが親権を持つかで争っている状況です。
裁判所に調停を申し込んだ場合「家庭裁判所調査官」が、どちらが親権を持つべきかを判断します。その際に「家庭裁判所調査官」が家庭訪問や学校訪問、また子供との面談等を行い離婚後の親子関係を考え調査して、決定していきます。
そんなとき「母親」と「父親」と、どちらが有利なのでしょうか?
母親が親権をもつケースは多くあります。特に乳幼児の場合、母親が有利とされています。なぜなら、母親の元で生活を送っている場合が多いためです。
子供の安定性を考えて、現状維持が優先されるため、そのまま母親と一緒に暮らすのが望ましいと客観的事情から判断される場合です。
そうは言っても「母親」が子育てできない場合もあります。それは、健康状態です。病弱だったり、精神的に不安定だったり、感情的に平穏を保つのが難しい場合、子育てに大きく影響します。
母親が自己コントロールができない場合、子育ては難しい、親権を持つにふさわしくないと判断されることもあります。
- あなたのまちの離婚相談“オススメコンテンツ”
- 『敷金・礼金・仲介手数料なしの家探し』
- 『離婚の悩み』
- 『借金の悩み』
むしろ「父親」が有利!?
「俺だって、子供のために働いている。母親が子育てをしている時間に、誰が外で稼いでいるのか!?」と、「父親」の方は思うかもしれません。
確かに子どもを養育する上で、経済的な要素はとても大切なことです。子育てにはお金が必要だからです。
お金があるからといって幸福が約束されるわけではありませんが、お金がないことで不幸な結末に陥る場合が多いのも事実なのです。
しかし経済的な強みしかない場合は、親権を持たない親(つまり自分)が「養育費」という形で子供を育てる義務を果たしていくことで、相手の方が経済力が無い場合でもこの養育費で子どもを育てることができると判断されるため、相手方の経済力がないことが弱みではなくなってしまうのです。
言い方を変えると、相手方に経済力が無くてもあなたが養育費を払うことで相手方の経済力がないことが帳消しになってしまうのです。
こうなると経済力だけでは「父親」の方が有利となる材料にならないのです。
現実をみると
「母親」と「父親」の親権を取得した割合(離婚調停・審判までいったケース)を数字でみると、「母親」が「9」にたいして、「父親」は「1」しかありません。
つまり世の中の流れから判断すると、「父親」が親権を取得するのはとても困難なことなのです。
- あなたのまちの離婚相談“オススメコンテンツ”
- 『敷金・礼金・仲介手数料なしの家探し』
- 『離婚の悩み』
- 『借金の悩み』
生活がどう変わるのか!?
離婚に伴い、住居などの変更はあるでしょうか?引っ越しすれば、学校も変わります。
実家に子供を連れてもどりますか?実家の両親は子育てに協力してくれますか?
近くに親族がいて助けてくれますか?子育てに、どれほどの時間が避けるでしょうか。
ひとり親が子育てをすることは、とても大変なことです。
まして生活が変わるとなれば子供の情緒にも大きく関わります。慣れ親しんだ家や学校など、環境が安定していることは子供にとって大切なことです。
生活が変わるのですから、お金の使い方も時間の使い方も変わってきます。
生活が変わっても、安定して子育てができるのか、服装、栄養、学校の宿題など子供に気を配らなければならないことはたくさんあります。
- あなたのまちの離婚相談“オススメコンテンツ”
- 『敷金・礼金・仲介手数料なしの家探し』
- 『離婚の悩み』
- 『借金の悩み』
愛情が大きい方が有利!!
最終的には「子供を大切にできるのは、誰か」ということですので、親の愛情の大きさは絶対に必要です。
愛情の大きさによって、愛情の表し方もどこまでのことをできるのか、ということも変わってくるでしょう。
「父親」であっても、仕事を調整して子供と過ごす時間を大切にし、子育てに時間を十分に割いているのであれば、客観的事情として評価されるでしょう。
愛情を子供優先に生活を送っているかどうか、という事実として表すことができるのです。子どもを育てる環境が整うのであれば「母親」も「父親」もどちらも親権者としてふさわしいと判断される可能性があります。
これまでの子育ては、どのようなものだったのでしょうか?
子供が病気のとき「母親」として何ができたでしょうか?
子供の学校行事のとき「父親」として何ができたでしょうか?
掃除、洗濯など家事はしてきたでしょうか?
子供はどう思っているのか!?
乳幼児の場合「母親」が有利の場合が多いですが、10歳前後以上の子どもの場合は、どちらと住みたいかという子供の意見が尊重される場合もあります。
離婚後の親子関係が大切になってきますから、子供の気持ちを考えないわけにはいきません。「家庭裁判所調査官」も十分にそのことを考慮することでしょう。
つまり、条件としては「母親」でも「父親」でもなく「子供」にとって一番有利とされるものが親権を持つことになります。
子供も親のことはしっかり見ています。しかし、現在がどう変わって新しい生活を築いていくかという見通しを立てることまでは、難しいことです。
様々な事情を考慮して家庭裁判所は判断し決定します。
将来どうするのかということを具体的に考えている親でなければ、親権を持つ親はつとめられません。
- あなたのまちの離婚相談“オススメコンテンツ”
- 『敷金・礼金・仲介手数料なしの家探し』
- 『離婚の悩み』
- 『借金の悩み』